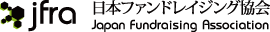【オンライン開催】体系的にファンドレイジングを学べる唯一の基礎講座「准認定ファンドレイザー必修研修」
| 開催20241/25Thu. |
この研修では、ファンドレイジングの知識を体系的にまとめた約400頁のテキストを用い、組織の成長戦略、寄付・会費・助成金を得るための戦略や基本スキルを学びます。ファンドレイジングの全体像を理解でき、自分の体験や個々の研修などで得る学びを体系化することができます。
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| ファンドレイジング概論 | ・フィランソロピーの概念とファンドレイジングの定義 ・ファンドレイザーの定義 ・認定ファンドレイザー資格制度の意義と目的 ・日本の寄付とボランティア |
| ファンドレイジング実践の体系と基盤 | ・戦略的なファンドレイジングの考え方 ・NPO の財源の特徴と相乗効果 ・潜在力とポジショニングの把握 ・成長・発展戦略(中期計画)の策定 ・共感メッセージ力の強化 ・心理的効果とファンドレイジング ・ファンドレイザーの倫理(法的・社会的・職業的) ・ファンドレイジング行動基準・ガイドライン ・寄付者の権利の尊重 ・理事・ボランティアの参加とファンドレイジング ・評価とリスク管理 |
| 日本の政策・制度の特徴 | ・税制の概要 |
| ファンドレイジングの個別スキル | ・寄付メニュー設計のポイント ・様々な寄付プログラムの種類(キャンペーン型/イベントを使ってのファンドレイジング/もったいない系寄付/募金箱/マンスリーサポーター制度/企業からの支援/大口寄付/遺贈) ・魅力的な会員制度設計 ・インターネットを活用したファンドレイジング ・寄付者データベース ・助成金・補助金の性格と特徴 ・助成金金申請の5つのステップ ・申請書の書き方の基本 ・助成事業を進めるうえでの重要なポイント ・事業収入 ・融資・疑似私募債 (事業収入・社会的投資・融資・議事私募債については、准認定ファンドレイザー必修研修では取り扱いません) |